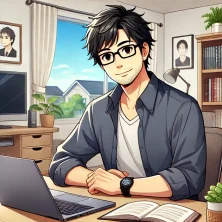投資初心者に人気のある積立NISAですが、「積立nisa やめたほうがいい 知恵袋」で検索する人が増えています。
その背景には、やめたほうがいい理由やカモにされて後悔した経験を知りたいという関心があるようです。
特に「月1万円の積立は意味ありますか?」という疑問や、やめたほうがいい人の特徴について悩む声も多く聞かれます。
この記事では、カモとならないための注意点を解説しつつ、貯金の代わりになりますか?といった疑問にも答えます。
また、後悔したブログに学ぶ成功ポイントを参考に、積立NISAの正しい理解を深める手助けをします。
ポイント
・積立NISAをやめたほうがいい理由とその背景
・カモにされて後悔しないための注意点
・積立NISAが貯金の代わりになるか
・後悔した人の失敗談から成功ポイントを見つける
Contents
積立nisaはやめたほうがいい?知恵袋で話題の理由

メモ
・やめたほうがいい理由は何ですか?
・カモにされて後悔した経験
・月1万円の積立は意味ありますか?
やめたほうがいい理由は何ですか?
積立NISAをやめたほうがいい理由として挙げられる主な要因は、制度や運用方法が合わない場合や、個々の状況によっては投資を継続することが難しいことです。
長期的な投資を前提
まず、積立NISAは長期的な投資を前提としており、短期間での成果を求める方には不向きです。
積立NISAでは少額からの積立が基本となり、20年間の非課税運用期間を活かすことで利益を最大化します。
新NISAは一括か積立か、どっちがいいか?で言えば、ぶっちゃけると一括が一番良いと思います。理由としては、NISAは20年30年と長期に渡って資産形成するのを前提としているので、であれば1日でも早い方が得だからです。為替を考慮しても株価上昇が上回るでしょう。…
— Pan* (@PanF5) December 29, 2024
旧積立NISA枠は20年の期限があるので、20年経過すると非課税枠から課税枠に切替わる。2020年から積立してるので2040年までには非課税、それ以降は課税される。どこかで暴落が発生した場合、含み損になり売りタイミングがなくなる。2040年以降だった場合含み益になっても20%の課税が発生する。
— 斎藤 (@dj_xeeenooo) December 28, 2024
このため、すぐに結果が見えないことが理由でモチベーションが続かず、途中でやめてしまうケースが考えられます。
元本保証がない
また、積立NISAは元本保証がないため、資産が値下がりする可能性があります。
これは、投資初心者が最初に抱える不安の一つであり、特に市場の変動に敏感な人にとっては、精神的な負担となることもあります。
リスクを十分に理解せずに始めてしまうと、相場が下がった際に損失を恐れて売却し、結果的に損をすることも考えられます。
選択肢の制限
さらに、積立NISAは制度上、投資信託やETFにしか投資できません。
そのため、特定の金融商品や直接株式への投資を希望する方にとっては、選択肢が制限されている点がデメリットです。
自分の投資スタイルに合わない場合、制度そのものをやめた方が良いという結論に至ることも少なくありません。
一括と積立の歴然たる差を見よ NISA 投資方法 × 投資先 の含み益比較表 #NISA… pic.twitter.com/3g4z8A4RAt
— ボイトンボイ@投資日次更新 (@SP500TARO500) December 30, 2024
余剰資金の問題
最後に、余剰資金がない状態で積立NISAを始めることもやめたほうがよい理由に含まれます。
生活費を圧迫してまで投資をすることは本末転倒です。
投資は余剰資金で行うのが基本であり、無理な運用は長期的な資産形成に悪影響を及ぼす可能性があります。
これらの理由から、自分の経済状況や投資目標に合っているかを慎重に検討することが重要です。
カモにされて後悔した経験
手数料が高い
つみたてNISAでカモにされて後悔した経験の主な例として、手数料の高い商品を選んでしまったケースが挙げられます。
特に初心者は金融機関や営業担当者から勧められる商品をそのまま購入しがちですが、これが結果的に不利な運用につながることがあります。
2.3.4.5.6月まで月3万円積み立て
FPに言われるがままやっていたので手数料が高いアクティブファンドを買っていた。
7月からはオルカンに月5万円の積立に変更
見事に高値掴むも狼狽売りはせず保持しています。— 株初心者がNISAを使うとこ (@zzzorzzzzz) October 8, 2024
対面型の金融機関は手数料が高めの商品を優先して提案する傾向にあり、その理由を理解せずに購入すると、運用益が手数料に消えてしまうこともあります。
一括投資をした
さらに、一括投資をしてしまい、短期的な相場変動で損失を出した例もあります。
つみたてNISAは少額を長期にわたり積み立てることを前提とした制度ですが、一括投資を行うことで市場の変動リスクを分散できず、大きな損失を抱えてしまうことがあります。
暴落くるらしい。ひぃ。米株は下がっても別に、むしろ嬉しいまであるけど(少額積立NISAのみの民なので)日経平均暴落はほんとキツい。辛い。暴落来る前から大損してるのよーーーたっけてーーーー🥲🥲🥲
— 酒爺 (@ggsakegg) December 18, 2024
来年のNISAは成長枠もつみたて枠も、一括ではなく毎日積立にしました🙌今年の暴落時に現金がなくて投資できなかったので、無理はせずコツコツ積み立てます😄チャンスがあれば買いには行きたいです☀️ pic.twitter.com/JS9Sn8DpCB
— ももき (@momokiiii1029) December 30, 2024
たとえば、市場が下落局面にあるときに一括で購入し、その後価格が回復せずに売却を余儀なくされたケースが後悔の要因となります。
情報不足や誤解
また、情報不足や誤解による後悔もよく見られます。
たとえば、「積立NISAなら損をしない」といった誤った前提で始めてしまうと、市場の下落に直面した際に現実とのギャップで不安を抱えます。
その結果、感情的に投資信託を売却してしまい、最適な運用期間を満たせず利益を損なうことがあります。
これを防ぐためには、投資する前に十分な情報を収集し、商品の手数料やリスクを理解することが大切です。
また、自分自身で選択する意識を持ち、営業トークに惑わされないようにすることも重要です。
月1万円の積立は意味ありますか?
積立NISAで月1万円の投資は、長期的な資産形成の観点から十分に意味があります。
複利で増える
月1万円という少額でも、継続的に投資を続けることで、複利の力を活かして資産を増やすことが可能です。
10年前に自己啓発でFP2級取得✨
最初投資始めて個別株はパッとしなかったけど
iDeCoは現在112.8万の積立が248万Overで136万のプラス💰️
今年から本格的に始めたNISAも損益80万以上プラス
お金が働いて複利効果で増えます!一人ひとりにあった稼がせ君のtips紹介できます✨
DM相談遠慮なくどうぞ! pic.twitter.com/hdn7Zief6T— あっとん🍊稼がせ君tips実践中!副業パパサポート (@atton_atton) December 29, 2024
たとえば、年間12万円(1万円×12か月)を年利5%で20年間運用した場合、最終的には元本240万円に対して約400万円程度の資産を築ける計算になります。
このように、少額でも長期で運用することで、将来的なリターンが大きくなるのが積立NISAの魅力です。
非課税制度
また、積立NISAの非課税制度は、月1万円の積立でも大きなメリットをもたらします。
通常、投資で得た利益には20.315%の税金が課されますが、積立NISAではその税金が免除されます。
これは、少額投資であっても節税効果を得られるという点で大きなメリットです。
特に長期的な運用では、非課税の恩恵が資産形成に与える影響は無視できません。
長期の投資
ただし、月1万円の積立は、短期間で大きなリターンを求める方には適していません。
積立NISAは、時間をかけて資産を育てる制度であり、早急な資金ニーズには対応できないためです。
そのため、月1万円の積立を始める際には、無理のない金額で継続することを重視し、必要な生活費や緊急時の資金に影響を及ぼさないよう計画を立てることが重要です。
将来の資産価値
さらに、月1万円の投資が将来的にどの程度のリターンを生むかは、選択する投資信託や市場環境に依存します。
リスクを抑えたい場合は、手数料の低いインデックス型投資信託を選ぶとよいでしょう。
これにより、コストを最小限に抑えつつ、安定したリターンを期待できます。
したがって、月1万円の積立は十分に価値がある投資方法であり、長期的な視野で考えることでその効果を最大化することができます。
積立nisaはやめたほうがいい?知恵袋に見る適切な判断

メモ
・やめたほうがいい人の特徴
・カモとならないための注意点
・貯金の代わりになりますか?
・後悔したブログに学ぶ成功ポイント
やめたほうがいい人の特徴
積立NISAは長期的な資産形成に向けた制度ですが、全ての人に適しているわけではありません。
やめたほうがいいとされる人の特徴を具体的に解説します。
一攫千金を狙う人
まず、短期間で大きな利益を求める人は積立NISAには向いていません。
この制度は少額・長期・分散投資を前提としており、即効性のあるリターンを期待する仕組みではありません。
そのため、短期的な株価変動に敏感な人や、一攫千金を狙う人は他の投資手法を検討したほうが良いでしょう。
生活費に余裕がない人
次に、生活費に余裕がない人も積立NISAを避けるべきです。
投資は余剰資金で行うのが原則であり、生活費を削って積立を行うことは長期的なリスクになります。
突然の出費が発生した際に資産を売却せざるを得なくなり、最悪の場合、元本割れする可能性もあります。
リスクを許容できない人
また、投資に対してリスクを全く許容できない人も積立NISAには不向きです。
この制度は元本保証がないため、運用成績によっては資産が減る可能性があります。
リスクを受け入れられない場合は、定期預金や国債のような元本保証の商品を選んだほうが安心です。
周りの意見に左右される人
さらに、自分で投資の判断をすることが難しい人や、知識を得るための時間を取れない人も積立NISAに向いていません。
商品の選択や運用方針の決定は自己責任で行う必要があるため、準備が不十分な状態で始めると期待通りの結果が得られない可能性があります。
これらの特徴に該当する人は、積立NISAの利用を一度見送るか、自分に適した資産運用の選択肢を探してみると良いでしょう。
カモとならないための注意点
積立NISAは初心者にも優しい制度として知られていますが、不適切な選択をするとカモにされるリスクもあります。
そのリスクを回避するための注意点を解説します。
手数料の高い投資信託
まず、手数料の高い投資信託を選ばないことが重要です。
積立NISAの対象商品は金融庁が厳選したものですが、その中にも手数料が高い商品があります。
一般的に、インデックス型投資信託は手数料が低く、安定した運用が期待できるため、初心者にはおすすめです。
一方で、手数料が高いアクティブ型投資信託は、リターンが必ずしも高いとは限らず、慎重に選ぶ必要があります。
金融機関の営業トーク
次に、金融機関の営業トークに流されないことが大切です。
特に対面販売の窓口では、金融機関側が利益を得やすい高コストの商品を勧めてくる場合があります。
新NISAの成長投資枠って名称、軽く罠だよなあ💭
積立枠で守り、成長投資枠で攻める、的な営業トークに嵌められそう…
全部守りでええねん— サブのむしさん (@MuShi_San_Mk13) January 6, 2024
銀行窓口で言われる積立NISA満額すごいですねーを真に受けてはならない。営業トークである😂
— 虚無 (@fuku_nonbiri) August 1, 2022
投資が庶民から搾りとる積もりだ、なんでそうなる?そりゃ証券会社の営業はセールストークで手数料高い投信買わせて搾りとるつもりだし銀行の営業も民間企業。だが積立NISAは手数料が低い投信のみでS&P500など米国株のみも有る。日本株外国株問わず時間を味方にして金融資産を増やしてくれという政策。
— National (@quizzuki) May 30, 2022
自分が納得できる商品を選ぶためには、事前に十分な情報収集を行い、投資信託の基本的な仕組みを理解することが欠かせません。
無理のない投資額
最後に、投資額は無理のない範囲で設定することを心がけましょう。
無理をして高額の積立を行うと、予期せぬ支出に対応できなくなるリスクがあります。
余剰資金の中で安定して積み立てることで、資産形成を長期的に続けやすくなります。
これらのポイントを守ることで、積立NISAを利用している人が不必要なリスクを避け、効率的に資産を増やせる可能性が高まります。
貯金の代わりになりますか?
積立NISAは資産運用の一環として注目されていますが、純粋な貯金の代わりにはなりません。
貯金と積立NISAは目的や特性が異なるため、両者を混同しないことが重要です。
元本が保証されない
まず、貯金は元本が保証されるという特性があります。
銀行預金であれば、たとえ金融機関が破綻しても一定額まで元本が保証されます。
一方、積立NISAは投資信託を用いた運用が基本であり、元本保証はありません。
市場の変動によって資産が増える可能性もあれば減るリスクも伴います。
このため、生活費や緊急時に必要な資金は、基本的に元本が保証される貯金で管理することが推奨されます。
運用期間と流動性
次に、運用期間と流動性についても違いがあります。
積立NISAは長期的な資産形成を目指すものであり、20年以上の運用を前提としています。
一方、貯金はすぐに引き出せる流動性が特徴です。
急な出費や予定外の資金需要に対応するためには、流動性の高い貯金が適しています。
資産形成のツール
しかし、積立NISAは将来の資産形成において強力なツールでもあります。
例えば、利回り5%で20年間運用した場合、複利の効果で資産が大幅に増加する可能性があります。
新NISA
S&P500から
積立投資枠
FANG+
成長投資枠
米国大型テクノロジー株式ファンド M7
に2024年7月から移行した結果です💴💰😊
分散し過ぎ注意⚠️
資産形成期は10銘柄以下の均等加重平均インデックス投資信託で、資産形成して行こう🚀 pic.twitter.com/1WtTNUlWJ7— 壱億貯男FANG+に1億円 (@ichiokutameo1) December 30, 2024
このため、生活費や予備資金を確保した上で、余剰資金を積立NISAに投資するのが理想的です。
貯金と積立NISAは相互に補完する関係であり、どちらか一方に偏るのではなく、目的に応じて使い分けることが賢明な資産管理といえるでしょう。
後悔したブログに学ぶ成功ポイント
積立NISAについてのブログには、成功体験だけでなく後悔の声も多く投稿されています。
これらの失敗談を分析し、成功するためのポイントを学ぶことができます。
短期間での利益を期待
まず、後悔の一つに「短期間での利益を期待してしまった」というものがあります。
積立NISAは長期的な運用が前提であり、数年の間に大きなリターンを得ることは難しいです。
そのため、短期的な視点ではなく、20年以上の運用を見据えて計画を立てることが重要です。
投資商品への知識不足
次に、「投資商品を十分に調べずに購入した」という後悔も多く見られます。
ブログでは、手数料の高い投資信託を選んでしまったり、自分のリスク許容度に合わない商品を購入したことを悔やむ声が挙げられています。
このような失敗を避けるためには、手数料が低いインデックス型投資信託を中心に選び、商品特性をしっかりと理解することが大切です。
無理な積立額を設定
さらに、「無理な積立額を設定してしまった」という意見も後悔の一因となっています。
生活費を削って積立を行うと、いざというときに資金が不足し、途中で投資をやめざるを得なくなるケースがあります。
積立額は無理のない範囲で設定し、余剰資金で行うことが成功のポイントです。
相場の変動に反応した
最後に、「相場の変動に一喜一憂して売却してしまった」という失敗談もあります。
積立NISAは市場の上下を耐えながら続けることで、長期的なリターンが期待できます。
一時的な値下がりを気にせず、運用を継続することが資産形成の鍵となります。
ブログの後悔談を参考にすることで、同じミスを避けながら、積立NISAを効果的に活用できるでしょう。
積立nisaはやめたほうがいい?知恵袋で話題のポイント
- 長期投資が前提で短期的な利益を期待する人には不向き
- 元本保証がないためリスクを許容できない人には向かない
- 投資信託やETFにしか投資できない制度上の制約がある
- 生活費に余裕がない人は積立NISAを避けるべき
- 営業トークに流されて高コストの商品を選ぶリスクがある
- 無理な積立額設定は資金計画を圧迫する可能性がある
- 手数料の高い商品を選ぶと運用益が減少する恐れがある
- 一括投資はリスク分散が難しく大きな損失を抱える場合がある
- 情報不足により投資リスクを理解せず後悔する人が多い
- 市場変動で不安になり売却してしまう失敗例がある
- 積立NISAは流動性が低く急な出費に対応しにくい
- 月1万円でも複利効果で資産形成が可能
- 非課税制度の恩恵で税金を節約できる点が魅力
- インデックス型商品はコストが低く初心者に適している
- 運用期間が長期であるため忍耐が求められる